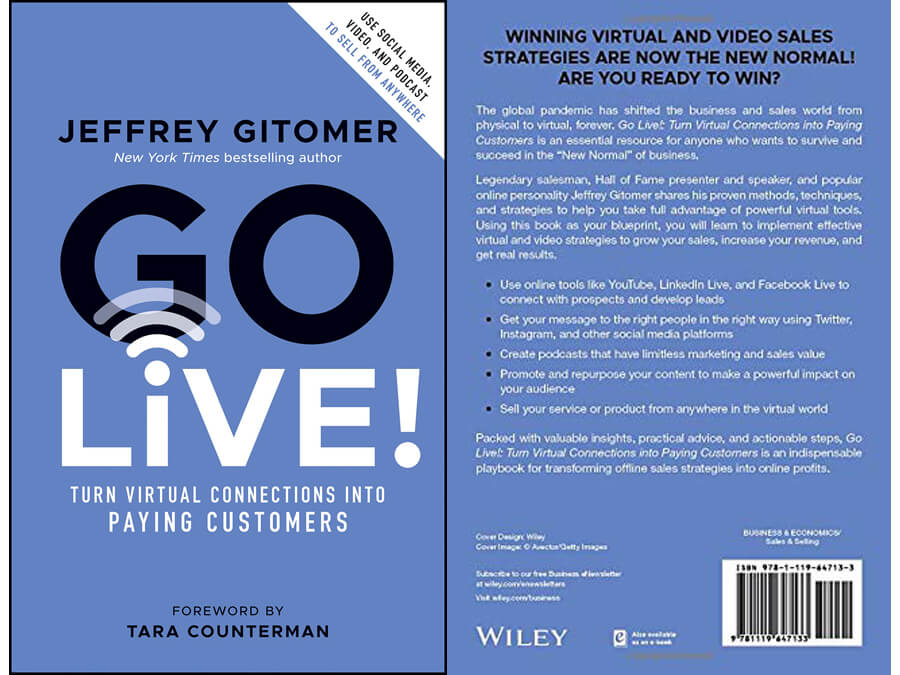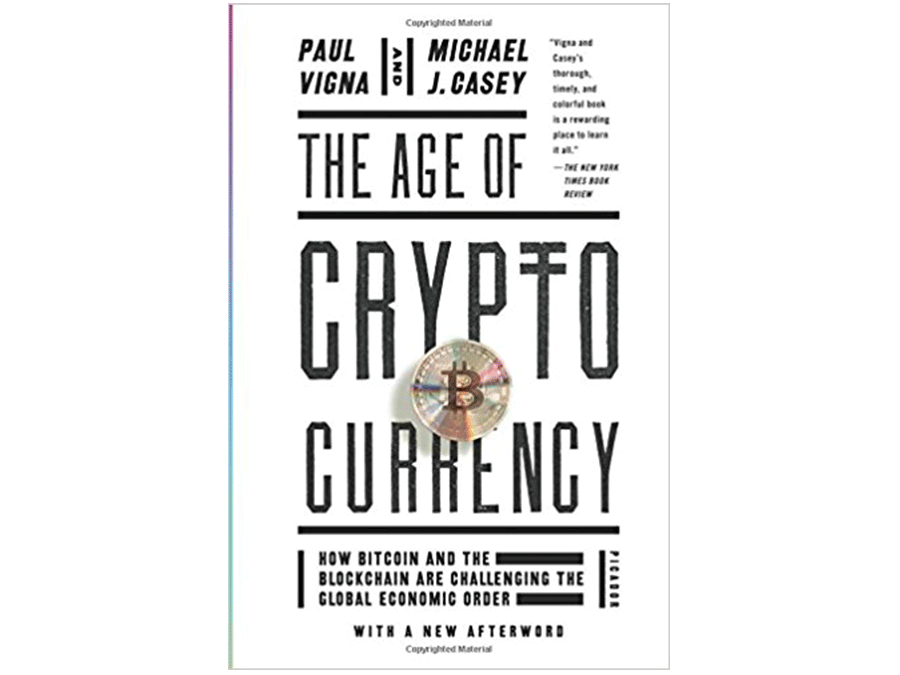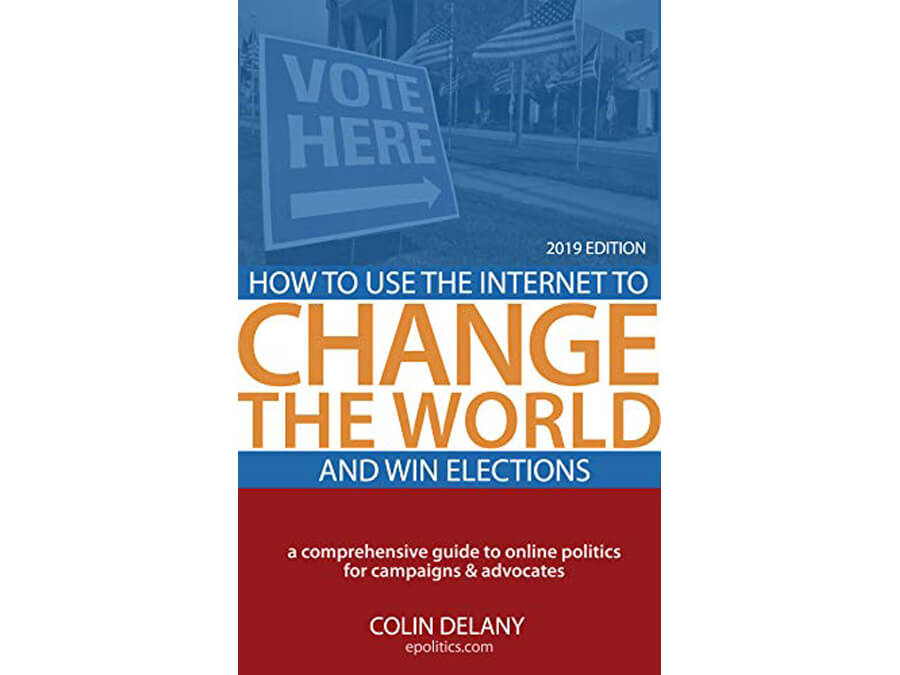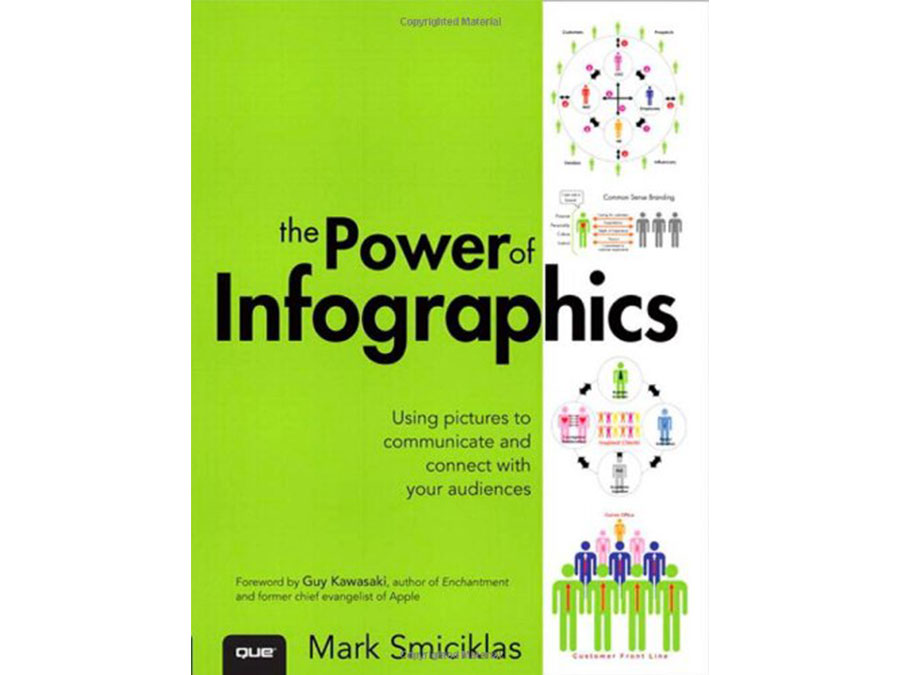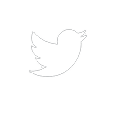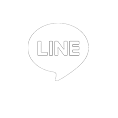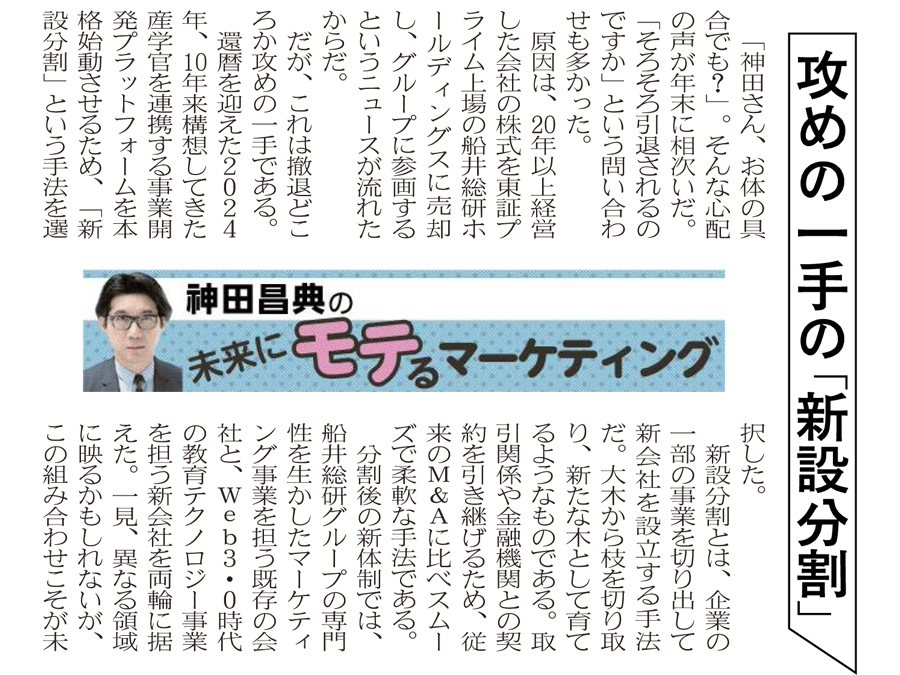
攻めの一手の「新設分割」 ― 日経MJ連載「未来にモテるマーケティング」25/1/27号
2025/2/3
「神田さん、お体の具合でも?」。そんな心配の声が年末に相次いだ。
「そろそろ引退されるのですか」という問い合わせも多かった。
原因は、20年以上経営した会社の株式を東証プライム上場の船井総研ホールディングスに売却し、
グループに参画するというニュースが流れたからだ。
だが、これは撤退どころか攻めの一手である。
還暦を迎えた2024年、10年来構想してきた産学官を連携する事業開発プラットフォームを本格始動させるため、
「新設分割」という手法を選択した。
新設分割とは、企業の一部の事業を切り出して新会社を設立する手法だ。
大木から枝を切り取り、新たな木として育てるようなものである。
取引関係や金融機関との契約を引き継げるため、従来のM&Aに比べスムーズで柔軟な手法である。
分割後の新体制では、船井総研グループの専門性を生かしたマーケティング事業を担う既存の会社と、
Web3.0時代の教育テクノロジー事業を担う新会社を両輪に据えた。
一見、異なる領域に映るかもしれないが、この組み合わせこそが未来を開く。
なぜか。これからの日本を支えるのは「事業開発力」だ。
探究学習が本格化する教育現場では、小学生までもが社会課題解決型プロジェクトを立案する。
ここで不可欠なのが、実務家の専門的支援である。
子どもたちの柔軟な発想をビジネスの知見で育む――。
この連携が実現すれば、世代を超えた社会変革の連鎖が始まる。
具体例を一つ挙げよう。
ある地方都市で、中学生たちが地域資源を生かした新商品開発に取り組んだ。
生徒たちは地元企業の商品開発者と共に、マーケティングやブランディングの手法を探究しながら商品化に結びつけた。
この過程で生まれた若者目線のアイデアは、企業の固定観念を打ち破り新たな名産品を生んだ。
また、プロジェクトに関わった生徒の多くが、将来の職業選択として地域産業に強い関心を示すようになった。
これこそが、教育と産業の相乗効果である。
今、あなたの会社は、進化する教育現場とどれだけ接点を持っているだろうか。
人材難の時代、若い世代との接点は企業成長の生命線となる。
この接点づくりから、企業と地域を結ぶ新たな価値創造が始まるのだ。
この分割により、私は2社を経営することになる。
苦労は倍増?
否、協力者が倍増したことで、各分野での専門性が高まり自分の強みにフォーカスできるので、大いに楽しみだ。
これこそが事業の選択と集中を実現する醍醐味である。
25年、人工知能(AI)はビジネスの標準となる。
その渦中で企業が成長するには、自社の強みを極限まで磨き、不要な部分を切り離す決断が求められる。
新設分割は、その有力な選択肢となる。
変革を恐れず挑戦すること。
それがAI革命に向かう、私たちの未来を開く。
変えるべきものと守るべきもの。
その見極めこそが、25年の企業の真価が問われる場面だと思う。