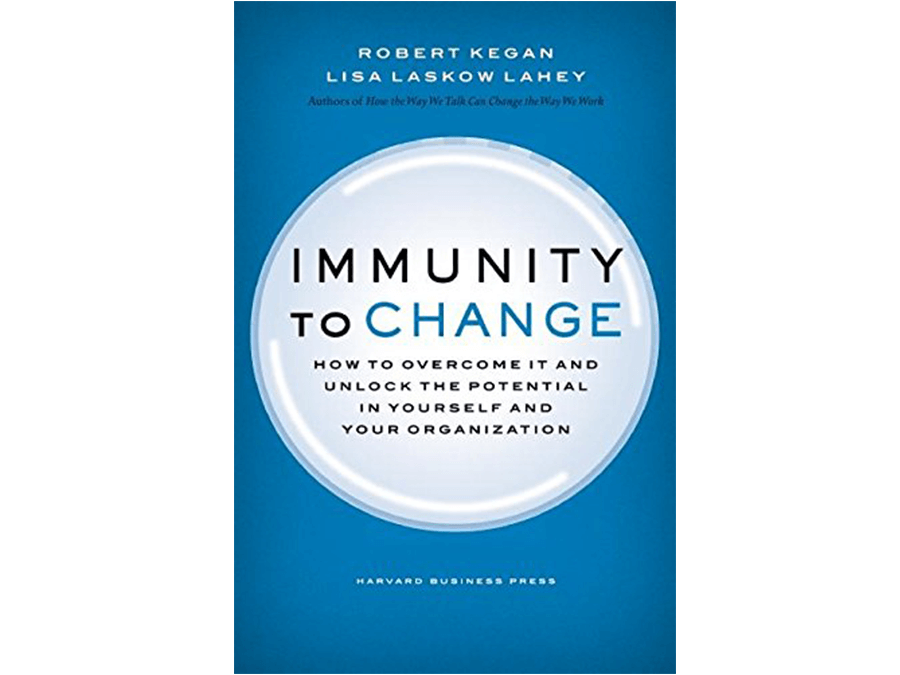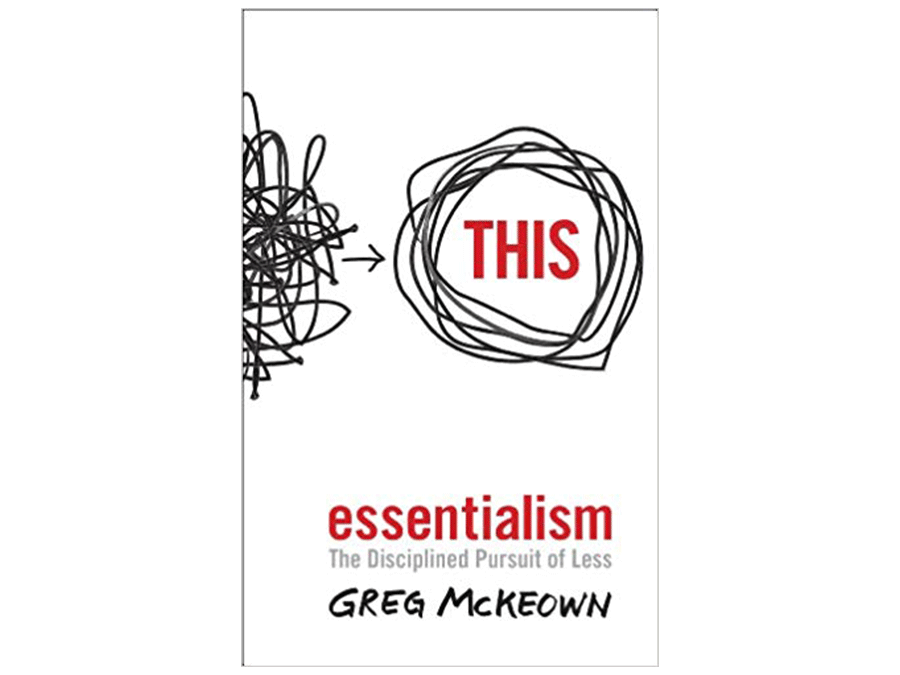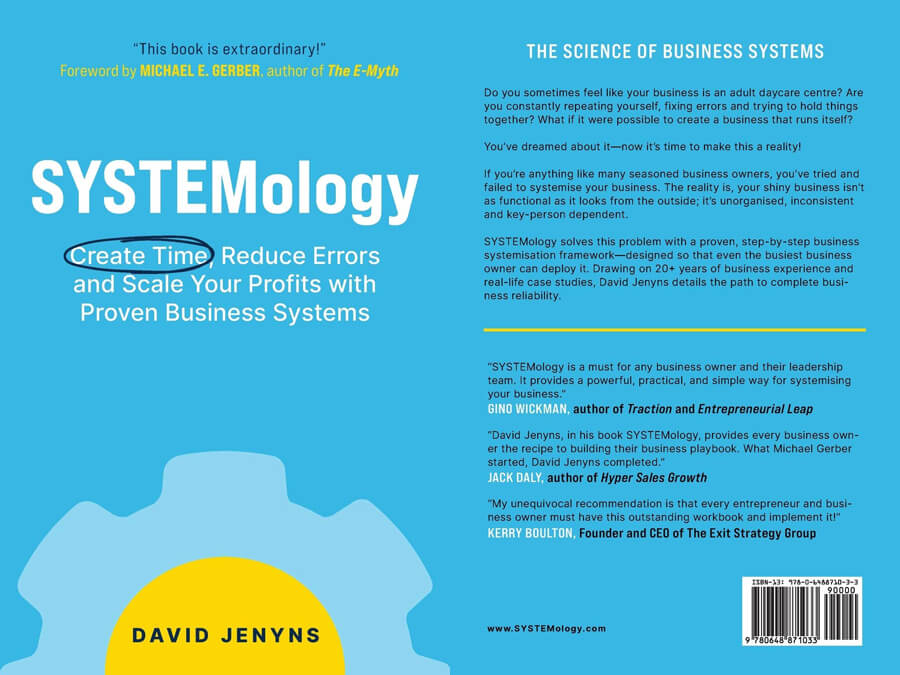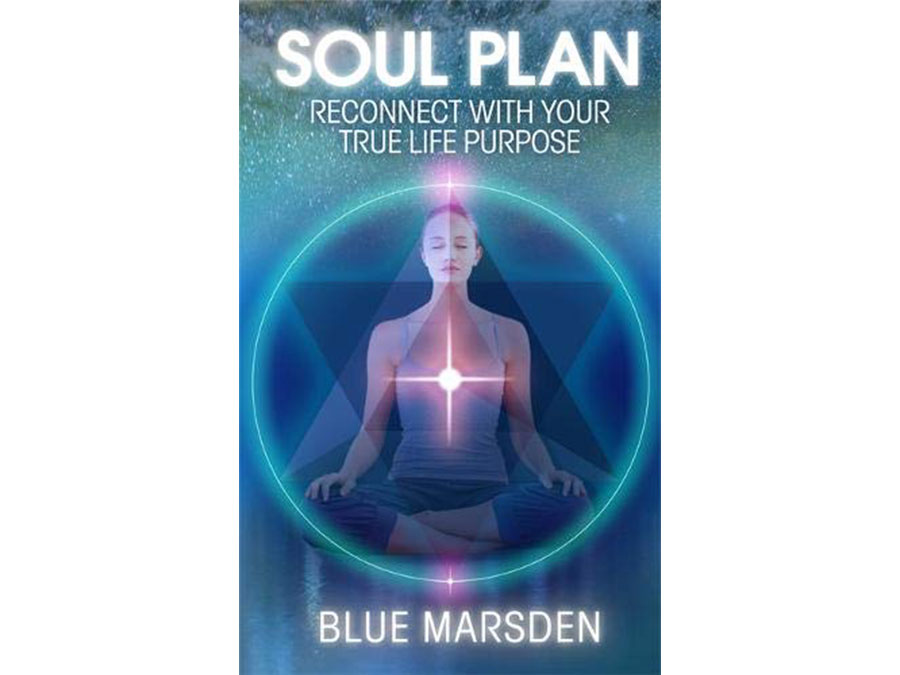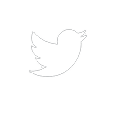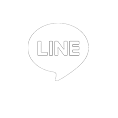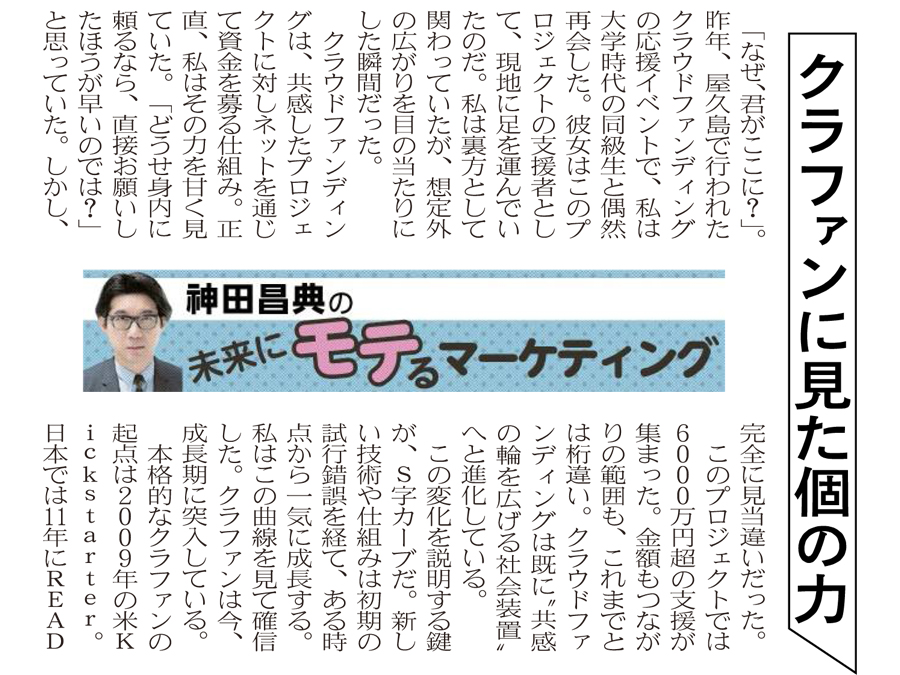
クラファンに見た個の力 ― 日経MJ連載「未来にモテるマーケティング」25/6/30号
2025/7/7
「なぜ、君がここに?」。
昨年、屋久島で行われたクラウドファンディングの応援イベントで、私は大学時代の同級生と偶然再会した。
彼女はこのプロジェクトの支援者として、現地に足を運んでいたのだ。
私は裏方として関わっていたが、想定外の広がりを目の当たりにした瞬間だった。
クラウドファンディングは、共感したプロジェクトに対しネットを通じて資金を募る仕組み。
正直、私はその力を甘く見ていた。
「どうせ身内に頼るなら、直接お願いしたほうが早いのでは?」と思っていた。
しかし、完全に見当違いだった。
このプロジェクトでは6000万円超の支援が集まった。
金額もつながりの範囲も、これまでとは桁違い。
クラウドファンディングは既に〝共感の輪を広げる社会装置〞へと進化している。
この変化を説明する鍵が、S字カーブだ。
新しい技術や仕組みは初期の試行錯誤を経て、ある時点から一気に成長する。
私はこの曲線を見て確信した。
クラファンは今、成長期に突入している。
本格的なクラファンの起点は2009年の米Kickstarter。
日本では11年にREADYFORやCAMPFIREが立ち上がった。
23年には国立科学博物館がREADYFORで「地球の宝を守れ」プロジェクトを行い、目標1億円に対し約9.2億円を集めた。
導入期と同じくらいの期間、成長期が続くとすれば、35年頃までは市場拡大が見込まれる。
この潮流は「集団から個人へ」という時代の変化とも重なる。
副業解禁は、もはや当たり前。
最近参加した大手企業の管理職候補者向けミーティングでは、参加者の7割が「脱サラしたい」と本音を漏らしていた。
理由を聞けば、やりがいのある副業を探しているという。
だが「やりがいのある副業って、それはもう本業じゃないか」と、経営者として思わず苦笑してしまった。
今、私は自身のクラファンを進めている。
企画、映像制作、ランディングページ(LP)、LINEやメールの運用――全てを担うのは独立した個人や副業人材だ。
共通言語は「マーケティング」。
最小限の打ち合わせでも仕事のクオリティーが高く、まるでライブツアーのスタッフのように期間限定で集まり爆速で動く。
組織では実現できないレベルの機動力。しかも全員が全体像を把握し、自ら手を動かす。
これが今の時代に求められる〝動ける個〞だ。
ビジネスに必要な道具――企画、動画、LP、決済、顧客情報管理(CRM)――は既にそろっている。
足りないのは構想力と行動力だ。
6月にはTikTokのライブコマース機能が日本でも提供されるなど、個人が活躍する舞台もさらに拡大している。
私はこの時代を「自律共創の時代」と呼んでいる。
企業に属しながらも副業でスキルを磨き、クラファンで思いを形にする。
それが、これからの生存戦略となる。
かつてはボーナスが出れば高級バッグや海外旅行に投じていたのが、今は夢をかなえるための自己投資と自己研さんに。
静かに、しかし確実に――そんな生き方を選ぶ人たちが増えてきている。