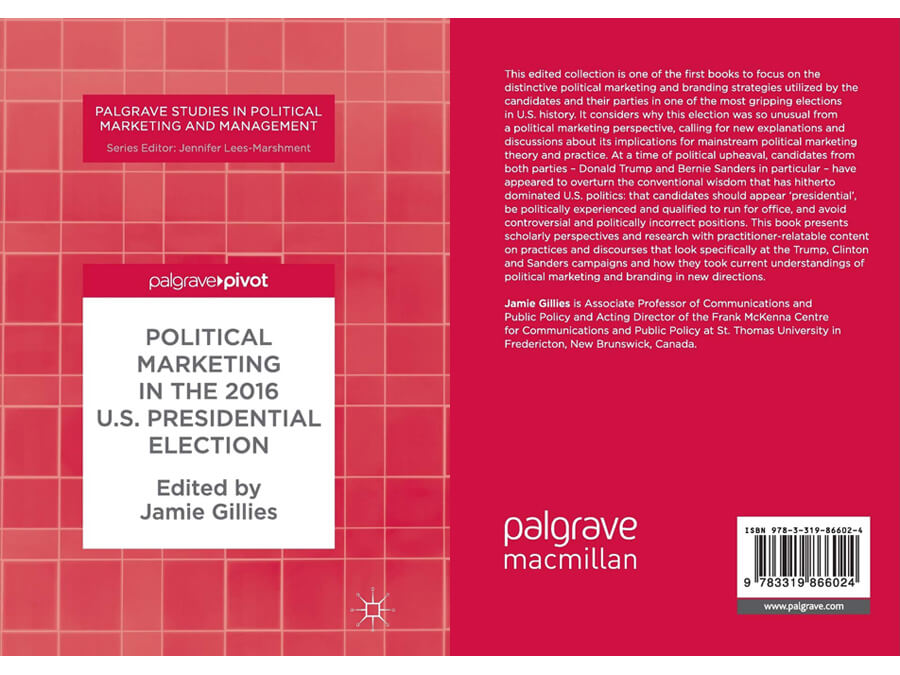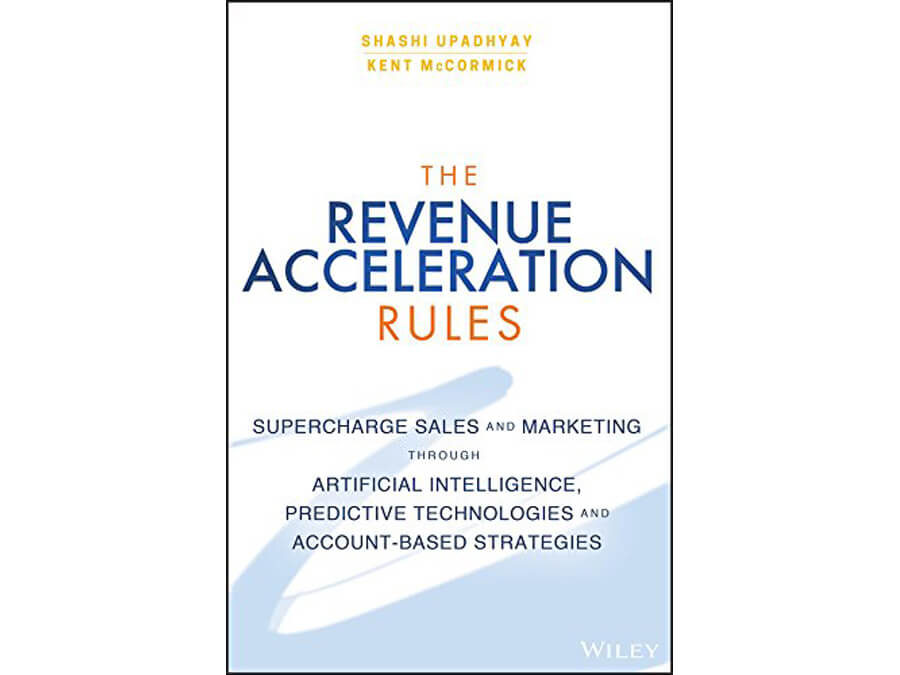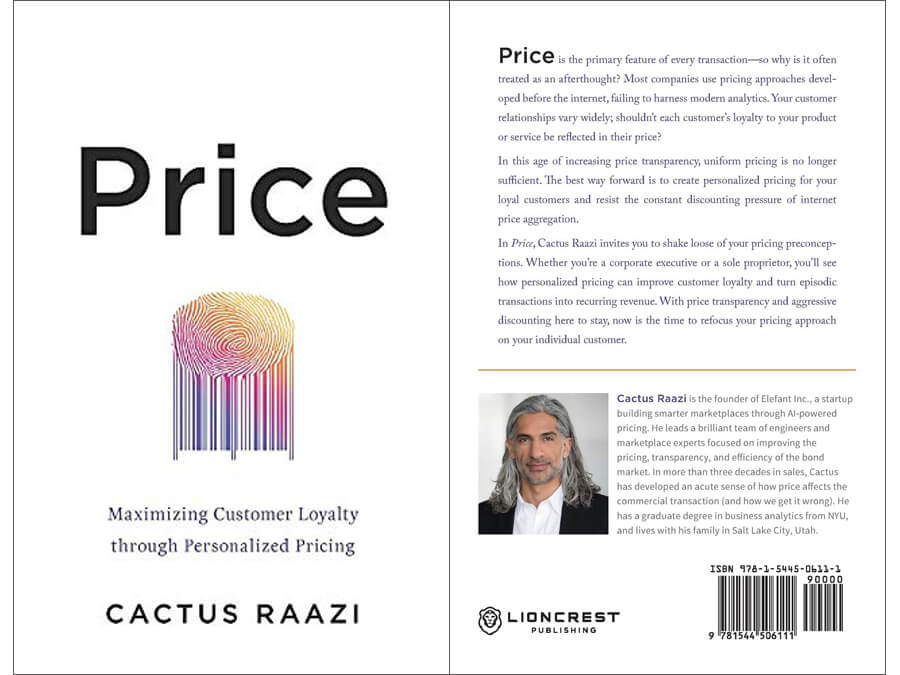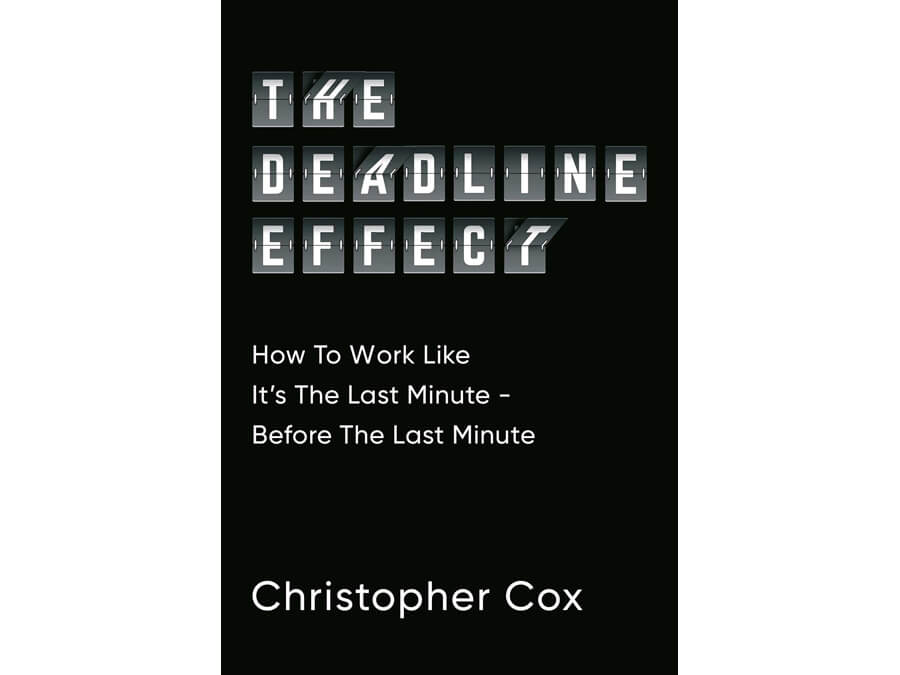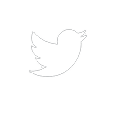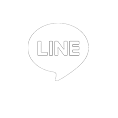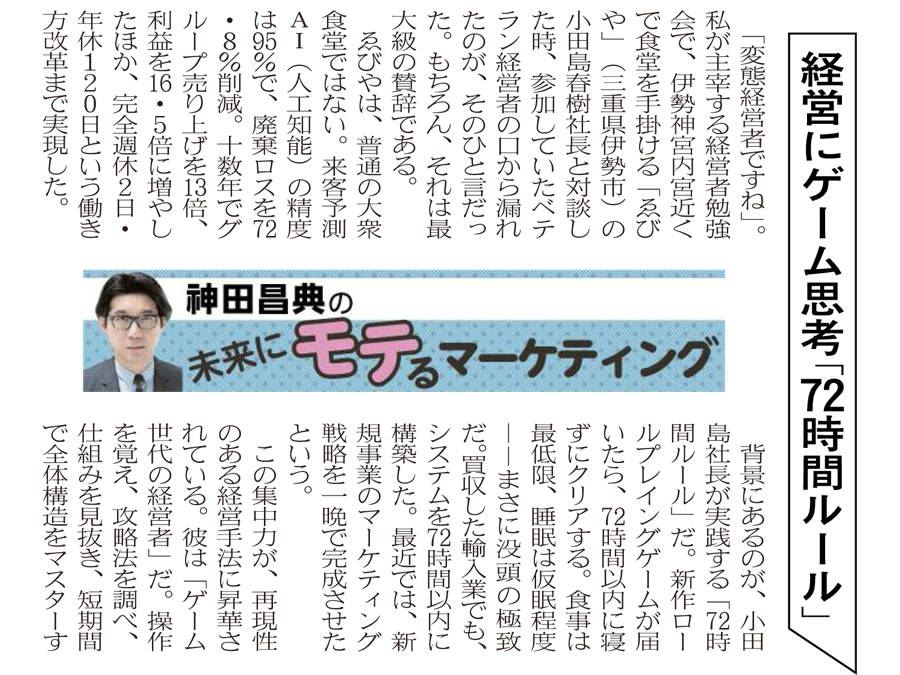
経営にゲーム思考「72時間ルール」 ― 日経MJ連載「未来にモテるマーケティング」25/7/13号
2025/7/21
「変態経営者ですね」。
私が主宰する経営者勉強会で、
伊勢神宮内宮近くで食堂を手掛ける「ゑびや」(三重県伊勢市)の小田島春樹社長と対談した時、
参加していたベテラン経営者の口から漏れたのが、そのひと言だった。
もちろん、それは最大級の賛辞である。
ゑびやは、普通の大衆食堂ではない。
来客予測AI(人工知能)の精度は95%で、廃棄ロスを72.8%削減。
十数年でグループ売り上げを13倍、利益を16.5倍に増やしたほか、
完全週休2日・年休120日という働き方改革まで実現した。
背景にあるのが、小田島社長が実践する「72時間ルール」だ。
新作ロールプレイングゲームが届いたら、72時間以内に寝ずにクリアする。
食事は最低限、睡眠は仮眠程――まさに没頭の極致だ。
買収した輸入業でも、システムを72時間以内に構築した。
最近では、新規事業のマーケティング戦略を一晩で完成させたという。
この集中力が、再現性のある経営手法に昇華されている。
彼は「ゲーム世代の経営者」だ。
操作を覚え、攻略法を調べ、仕組みを見抜き、短期間で全体構造をマスターする
――そのスキルセットが、そのまま経営の意思決定に応用されている。
実際、ゲームで培った「最適解を見つける思考法」が、店舗運営のあらゆる場面で威力を発揮している。
かつての経営は経験と人脈、そして根性の世界だったが、今や〝没頭〞をルール化できる人材が、
最速で成果を出す時代がやってきたのかもしれない。
その象徴が、ゑびやの「現場を神にする」設計だ。
ドリンクの残量はセンサーで検知され、ビジネスチャットツールのSlack(スラック)に自動通知される。
在庫は自動で補充され、アンケートはリアルタイムで分析される。
売り上げ、客数、人時生産性は全てデータ化され、意思決定が現場で完結する仕組みができあがった。
さらに、スタッフの労働時間を3割削減したにも関わらず、顧客満足度が向上し続けている。
感覚と数字を統合し、現場が経営者のように判断する構造。それがゑびやの正体だ。
だが、そこで終わらない。現在、ゑびやグループの飲食業比率はわずか25%。
残りは小売り、店舗分析のSaaS(ソフトウエア・アズ・ア・サービス)事業、教育、玩具輸出業、投資事業など
20種以上の事業が、現場起点の知覚とデータで接続されている。
例えば食堂で得られた顧客データは、教育事業のカリキュラム開発に活用。
輸入業の物流ノウハウは電子商取引(EC)事業の配送最適化に応用される。
一見すれば無関係な多角化に見える。
だが実際には、リスク分散と知の活用を同時に設計した分散型経営構造になっている。
利益16.5倍の先には、デジタルトランスフォーメーション(DX)ではなく〝経営の再構築〝がある。
彼は変態ではなく天才である。
問題は、天才がいるかどうかではない。
その天才の発想を、どこまで社会構造に変換できるか。
それこそが、成熟しきった日本に残された最後の成長戦略であると思う。