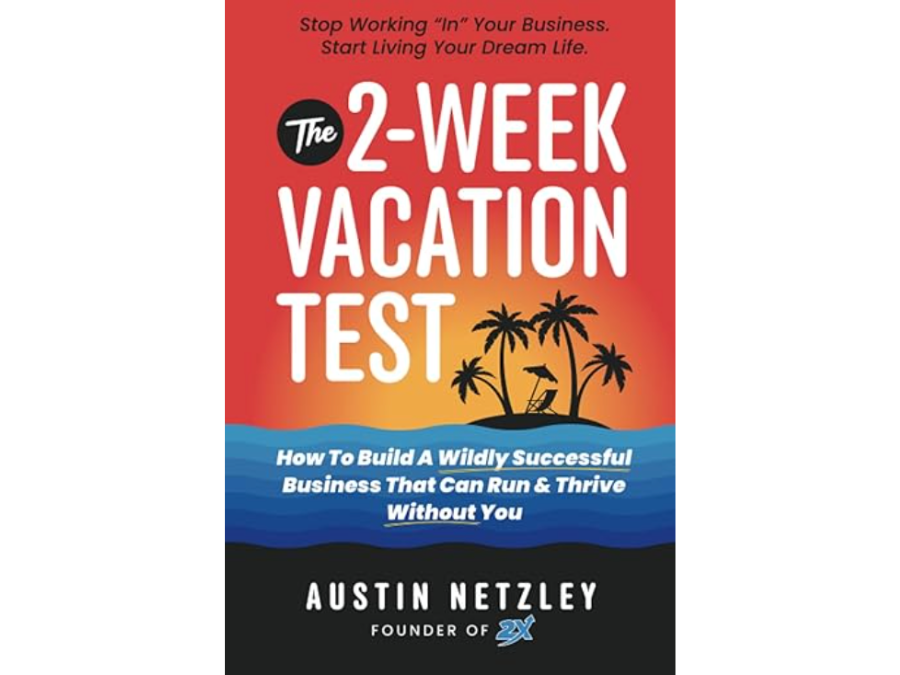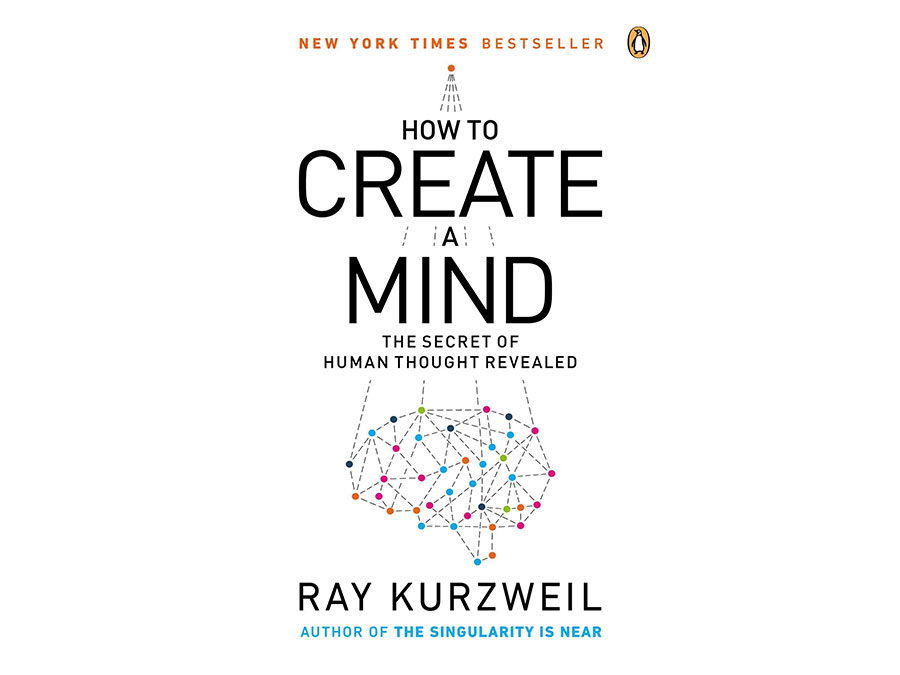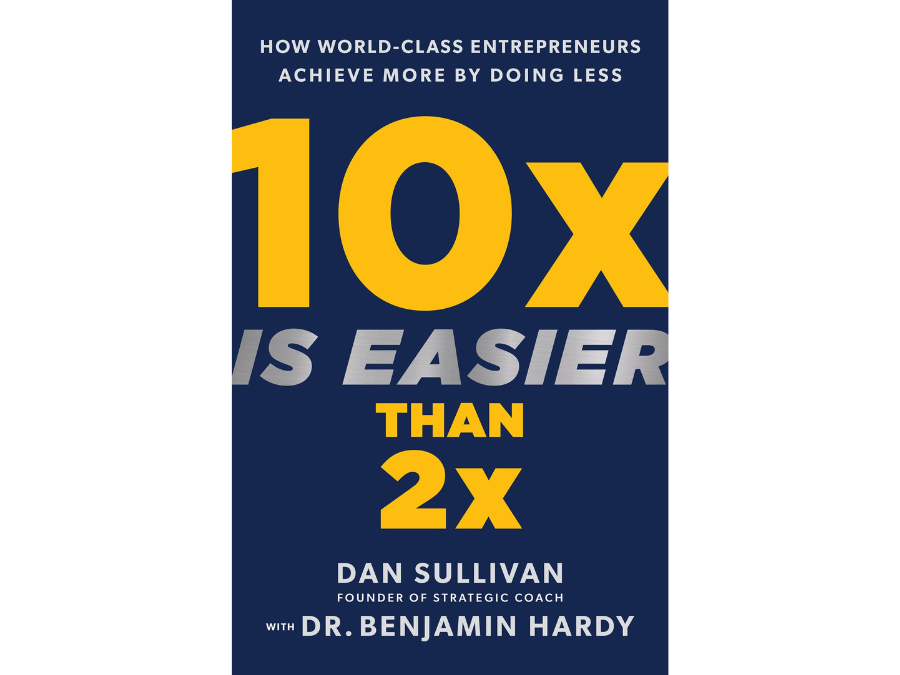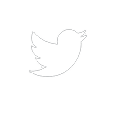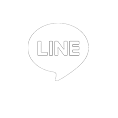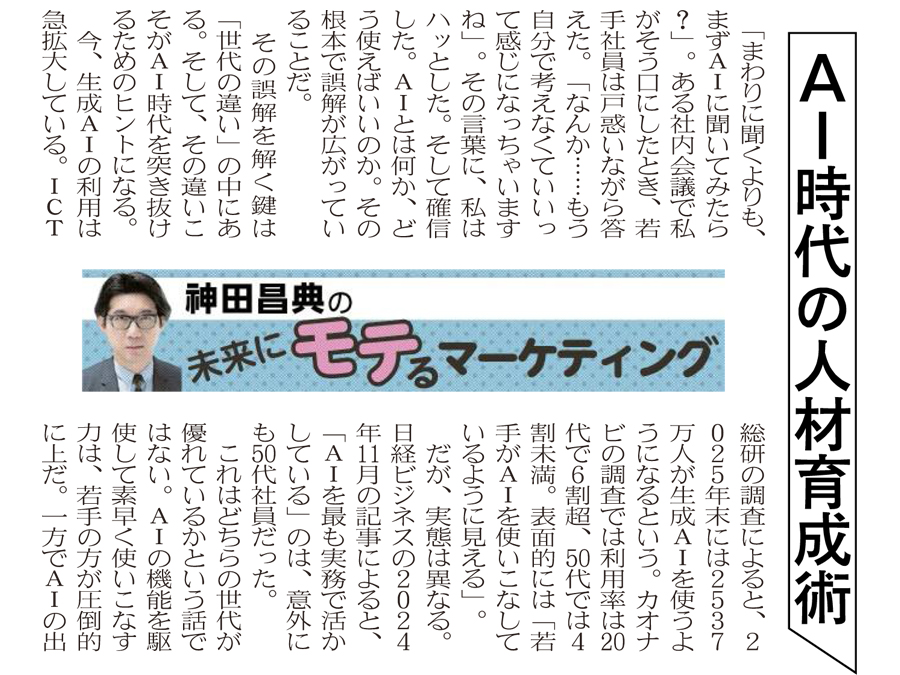
AI時代の人材育成術 ― 日経MJ連載「未来にモテるマーケティング」25/7/28号
2025/8/4
「まわりに聞くよりも、まずAIに聞いてみたら?」。
ある社内会議で私がそう口にしたとき、若手社員は戸惑いながら答えた。
「なんか……もう自分で考えなくていいって感じになっちゃいますね」。
その言葉に、私はハッとした。そして確信した。
AIとは何か、どう使えばいいのか。その根本で誤解が広がっていることだ。
その誤解を解く鍵は「世代の違い」の中にある。
そして、その違いこそがAI時代を突き抜けるためのヒントになる。
今、生成AIの利用は急拡大している。
ICT総研の調査によると、2025年末には2537万人が生成AIを使うようになるという。
カオナビの調査では利用率は20代で6割超、50代では4割未満。
表面的には「若手がAIを使いこなしているように見える」。
だが、実態は異なる。
日経ビジネスの2024年11月の記事によると、「AIを最も実務で活かしている」のは、意外にも50代社員だった。
これはどちらの世代が優れているかという話ではない。
AIの機能を駆使して素早く使いこなす力は、若手の方が圧倒的に上だ。
一方でAIの出力を実行可能な戦略へと翻訳する力は、経験がある昭和世代の方が深い。
そんな異なる強みを持つ世代の掛け算が、今後は極めて重要になる。
たとえばAIにターゲット企業のリストアップを頼んだとしよう。
リストの中から誰に会うかは、自分で決めるしかない。
その時、的確に判断できるのは昭和世代の方である。
この世代は紙・FAX・電話・飛び込み営業、そして店頭接客といったアナログな現場で、泥くさく結果を出し続けてきた。
そうして人と向き合い続ける中で蓄積されたのは、単なる経験ではない。
複雑な状況を前に、情報を整理・判断し動くための〝視点の引き出し〞である。
若手が持たないそれが、最適解を導き出す礎となるのである。
もっとも、ベテラン世代がすべきことは〝視点の引き出し〞を門外不出にすることではない。
私は今、〝視点の引き出し〞をAIに読み込ませ、自分の分身である「myGPT」を作って後進を育成している。
私は30代の頃、年2000件超のマーケティング相談に対応していた。
その中で必ず使っていた「5つの問い」がある。
①あなたの商品を20秒で説明できますか
②なぜ、お客様は他社ではなく、あなたを選んだのですか
③お客様はどんな場面で困っていましたか
④それを、なぜあなたが解決できるのですか
⑤その証拠はありますか
これらの質問で相手の中に眠る〝意味〞と〝価値〞を言語化し、判断につなげる。
この判断の流れをmyGPTに落とし込んだのである。
それによって、本来は経験によってしか身につかなかった〝判断の型〞をAIによって構造化・可視化でき、
数年かけて育成していた高度な判断力をもつ人材をわずか数週間で育てられるようになった。
だからこそ私は伝えたい。
ベテラン世代の経験は決して時代遅れではない。
状況に応じて適切な判断軸を選び出せる〝視点の引き出し〞こそが、いま最大の資産である。