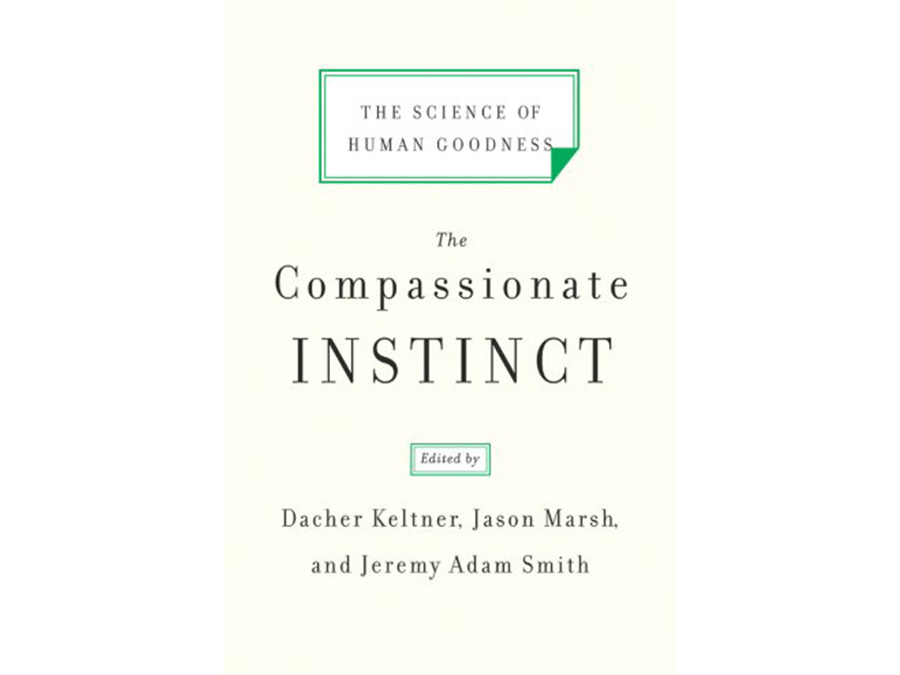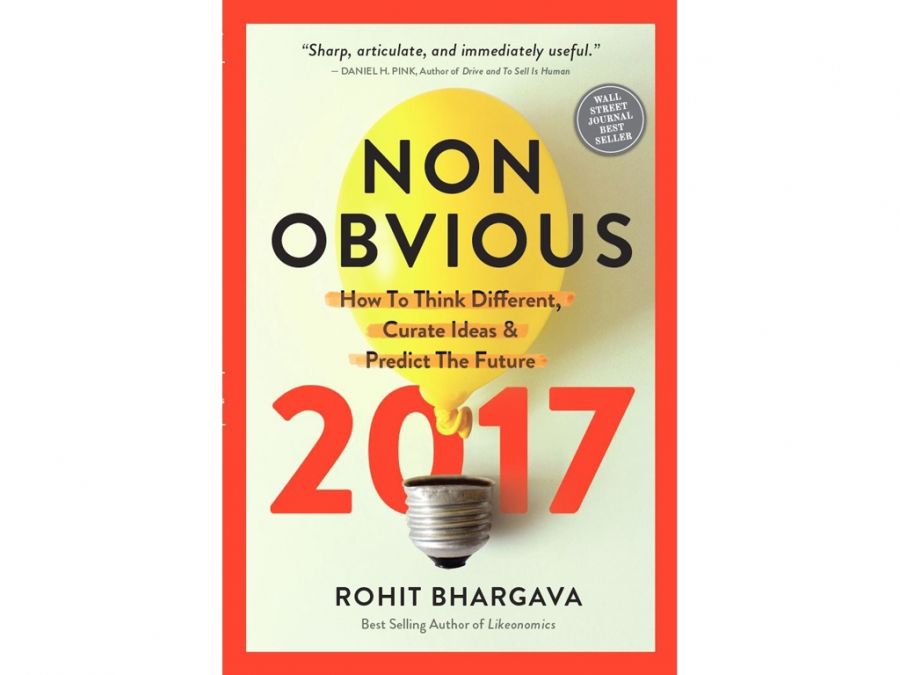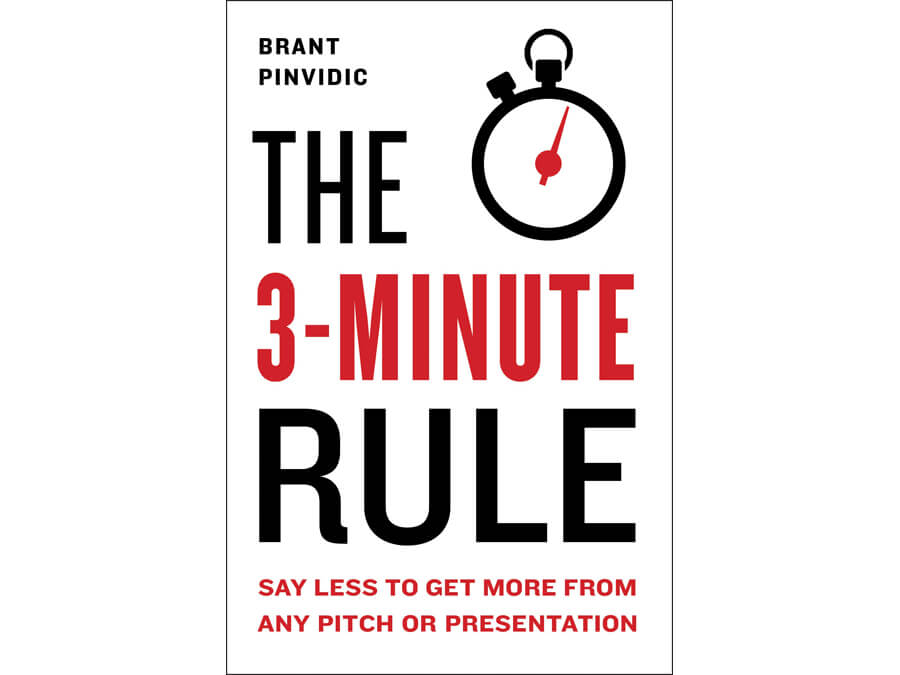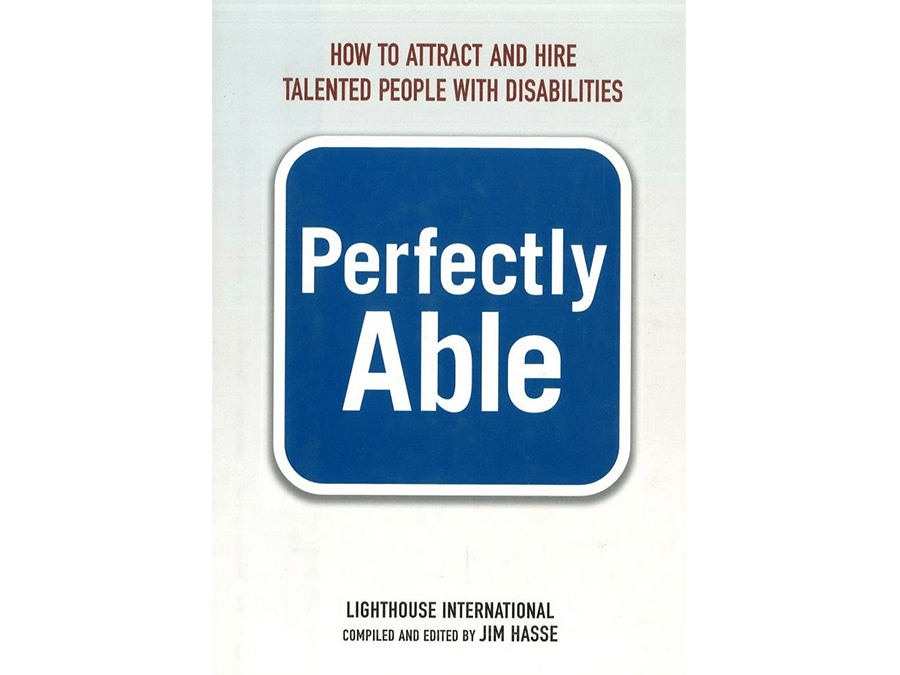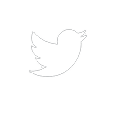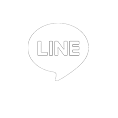2拠点居住、空き家活用に商機 ― 日経MJ連載「未来にモテるマーケティング」25/8/25号
2025/9/1
「私、家を2つ持っています」。こんなセリフを最近よく耳にするようになった。
かつては一部の富裕層や移住者だけの話だったが、今は違う。
サーフィンや芋掘りで海と畑を行き来しながら都市でも働く――
そんな暮らしを当たり前のように楽しむ人が増えてきた。
別荘の会員制シェアサービスを手掛けるSanu(サヌ、東京・目黒)の調査によると、
首都圏在住者の35%が二拠点生活に興味を持ちながら、実行しているのはわずか4%。
首都圏人口で計算すると、潜在的な「隠れ二拠点層」は推定700万人。
まだ市場としての伸びしろは相当ある。
一方、国の調査によると2023年の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%と過去最高を更新。
地方では20世帯中4世帯が空き家という地域もある。
増え続ける「余っている家」と「使いたい人」を結びつけられれば、社会課題を解決するビジネスが生まれる。
観光シーズンに依存したもろい経済から通年型の安定経済へ、そんな転換の可能性を秘めている。
ただ、現実には多くの空き家は老朽化が進み、改修コストという高い壁が立ちはだかる。
特に水回りと電気工事は高額になりやすく、
住宅関係者も「見える部分は工夫できても、ここだけはコストダウンが難しい」と口をそろえる。
そこで登場したのがモジュール型ユニットという発想だ。
水回りや電気設備を工場で一体化し、現地に据え付けることで工期もコストも圧縮。
これまでなら採算が合わなかった空き家改修を、現実的な選択肢に変えた。
この方法を展開している一例が、スタートアップのアドレス(東京・千代田)。
全国の空き家をシェアハウスなどに改装し
月9800円で2泊から宿泊できる定額住み放題サービス「ADDress」を提供している。
最大の難所である水回りは、モジュール型ユニットで突破。
拠点数は着実に増え、現在270拠点、2025年内には300拠点を見込む。
拠点には都市部のマンション型から地方の古民家、リゾート地の一軒家まで多様な物件がそろう。
会員の67.8%が年間30日以上滞在し、各地域で消費と交流を循環させている。
さらに各物件に「家守(やもり)」と呼ばれるコミュニティマネジャーを配置し、
行政や地域団体と連携しながら利用者と地元住民をつなぐ。
滞在者が地元企業から仕事を受注したり、住民向けワークショップを開いたりする例も増えている。
この仕組みは、地方自治体が注力する「関係人口」の創出にも直結する。
移住や定住と異なり、訪問型の関係人口はハードルが低く地域への貢献度も高い。
何度も訪れるうちに信頼が蓄積し、自然な交流が広がる。
二拠点生活が広がれば、地域の宿泊や商店だけでなく農業や伝統産業など眠っていた資源に光が当たり、
新たな雇用や人材の流動も生まれるだろう。
こうしたモデルが各地に根付けば、地域ごとに特色ある暮らしや働き方が生まれ、
国内外から人を引き寄せる力にもなる。
観光、教育、リモートワークなど多様な分野と結びつくことで、地域の経済基盤は一段と強固になるはずだ。