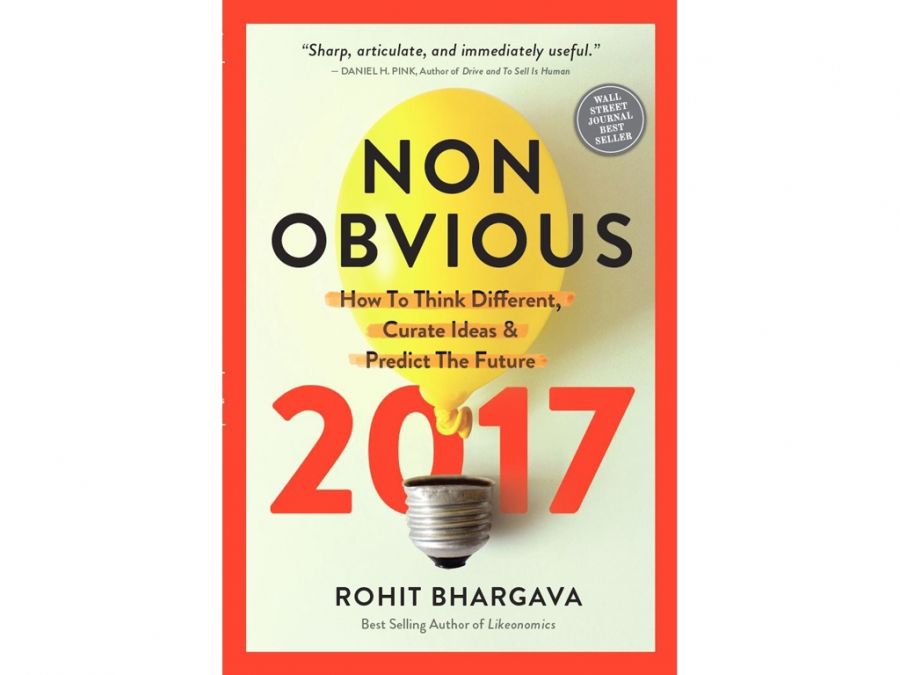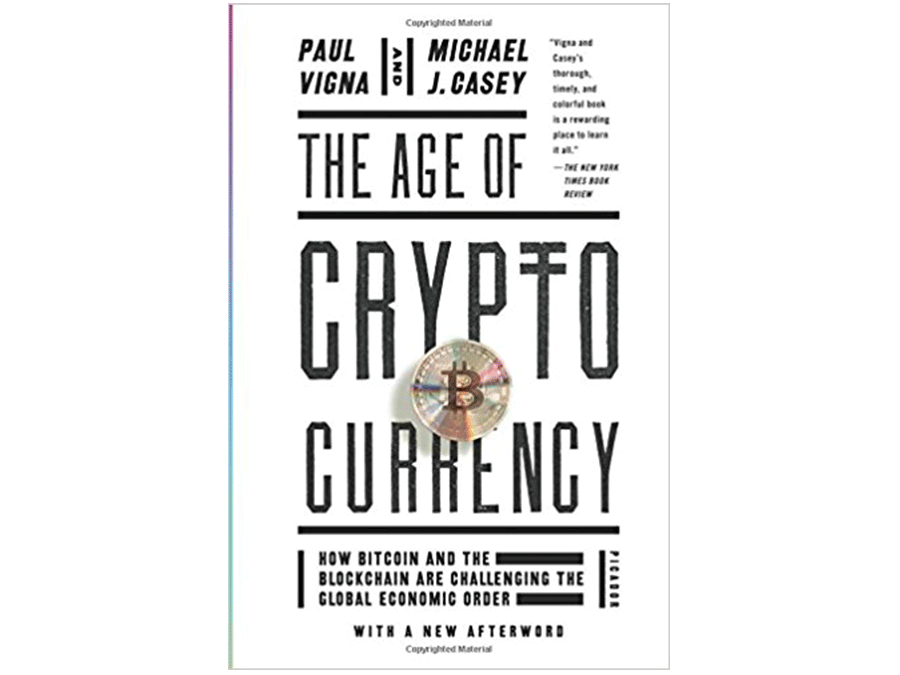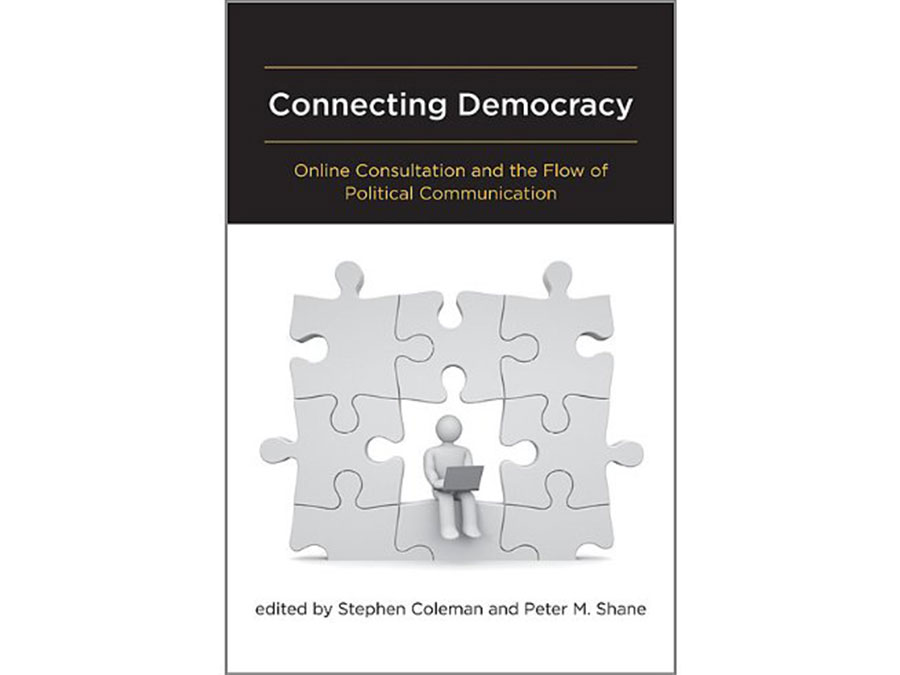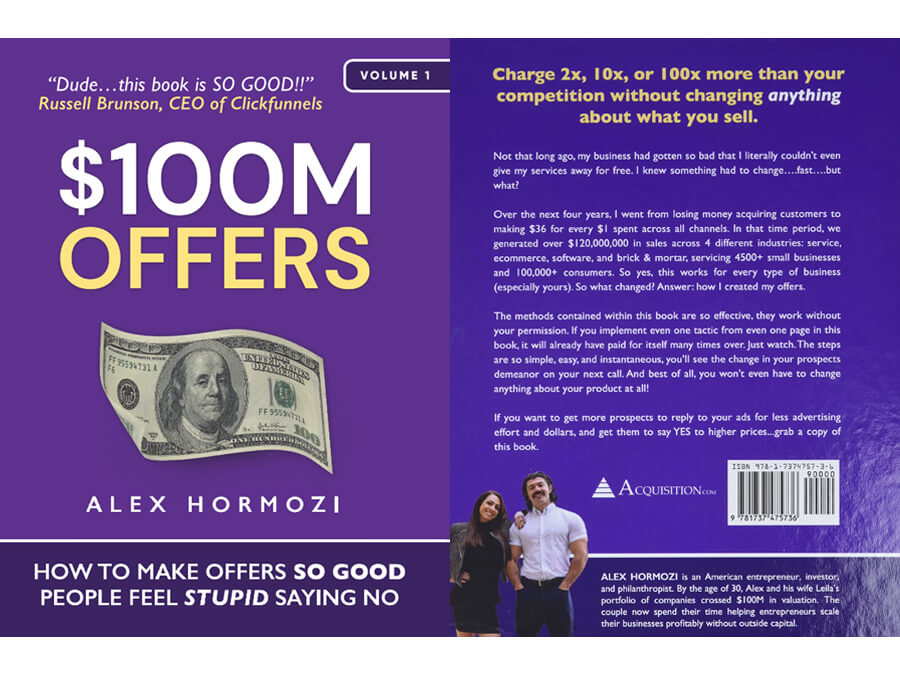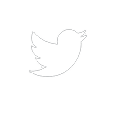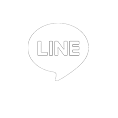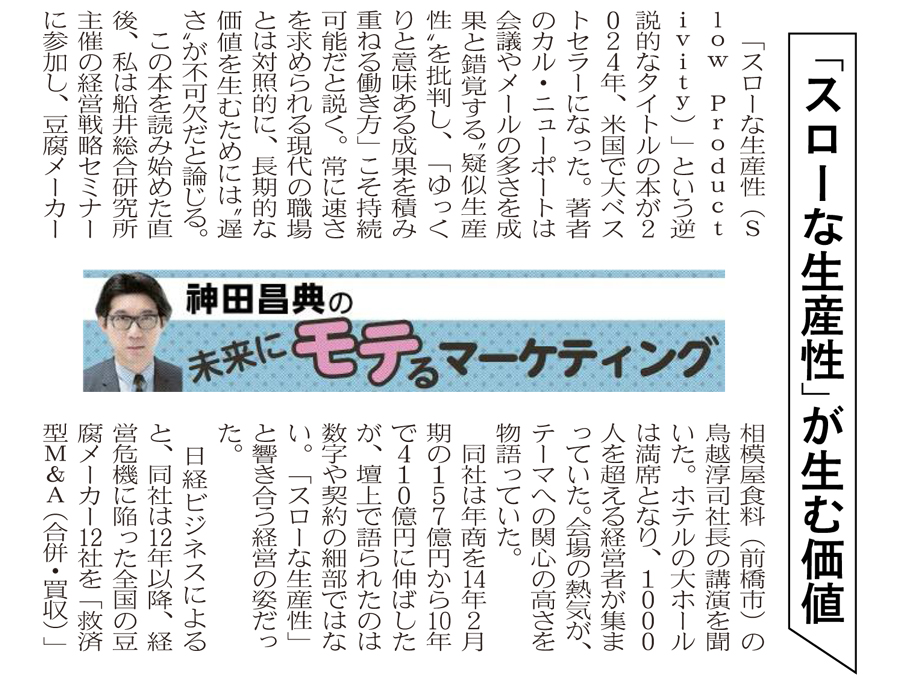
「スローな生産性」が生む価値 ― 日経MJ連載「未来にモテるマーケティング」25/9/8号
2025/9/15
「スローな生産性(Slow Productivity)」という逆説的なタイトルの本が2024年、米国で大ベストセラーになった。
著者のカル・ニューポートは会議やメールの多さを成果と錯覚する〝疑似生産性〞を批判し、
「ゆっくりと意味ある成果を積み重ねる働き方」こそ持続可能だと説く。
常に速さを求められる現代の職場とは対照的に、長期的な価値を生むためには〝遅さ〞が不可欠だと論じる。
この本を読み始めた直後、私は船井総合研究所主催の経営戦略セミナーに参加し、
豆腐メーカー相模屋食料(前橋市)の鳥越淳司社長の講演を聞いた。
ホテルの大ホールは満席となり、1000人を超える経営者が集まっていた。
会場の熱気が、テーマへの関心の高さを物語っていた。
同社は年商を14年2月期の157億円から10年で410億円に伸ばしたが、壇上で語られたのは数字や契約の細部ではない。
「スローな生産性」と響き合う経営の姿だった。
日経ビジネスによると、同社は12年以降、
経営危機に陥った全国の豆腐メーカー12社を「救済型M&A(合併・買収)」で再建してきた。
一般にM&Aは規模を追求し、生産効率やシェア拡大を目的とする。
しかし相模屋の選択は、その逆だった。
単なる規模拡大ではなく、地域ごとに根付いた「地豆腐文化」をよみがえらせ、
失われた職人技を取り戻すことに戦略の力点を置いた。
鳥越社長が再建の場で、まず掲げるのは「地元で親しまれてきた伝統の味を取り戻すこと」である。
職人たちがかつて誇りを持って作っていた一品を復活させる。それが社員の笑顔と自信を取り戻す出発点となる。
結果として生産効率や品質が高まり、経営が安定へと向かう。
意味ある成果はスローでなければ生まれない――この原則を実証する事例である。
こうした「意味による差別化」は、日本国内でも広がりを見せている。
長く「安さ=正義」とされてきた消費社会において、近年は「値上げ容認」の空気が強まっている。
背景には、むしろ安価すぎるものに対する警戒心がある。
価格だけを武器にした商品は
「どこかで無理をしているのではないか」「品質や文化が犠牲になっているのではないか」と感じさせるからだ。
だからこそ、意味や物語を伴った商品が支持される。
職人技を復活させる、地域独自の味を守り抜く――こうした意志が価格の裏に見えるとき、人々は安心して選択する。
値上げ容認の本質は、単なるコスト転嫁ではなく、
消費者が「価格の安さよりも意味を重視する時代」へと移行していることを示している。
生成AI(人工知能)が大量に情報を生み出す時代にあって、逆に意味が失われつつある。
だからこそ人間の役割は「意味を生成すること」にある。
意味とは何か。
それは単にモノを手に入れる効率ではなく、その商品の背景にある物語、人と人とのつながりである。
職人の技と地方独自の味を未来へと手渡すように、
購入者とのつながりに意味を見いだす営みへとビジネスの力点は確実にシフトしはじめた。