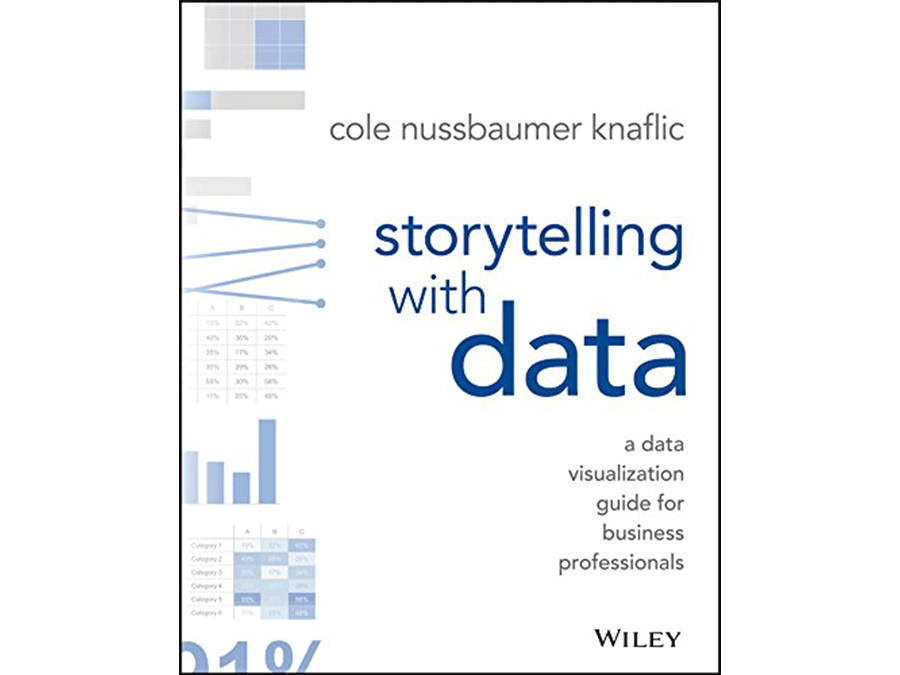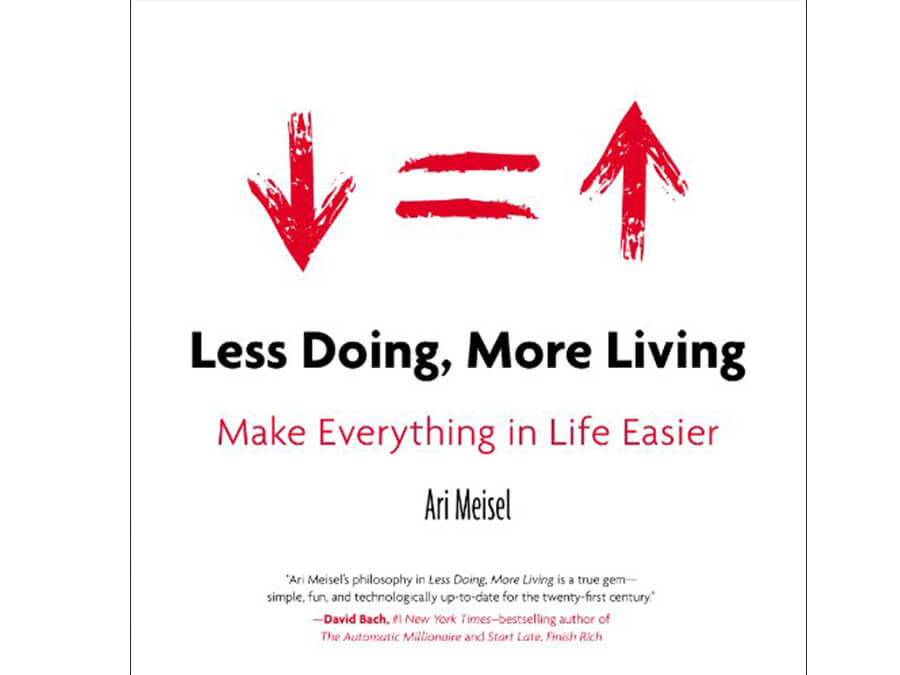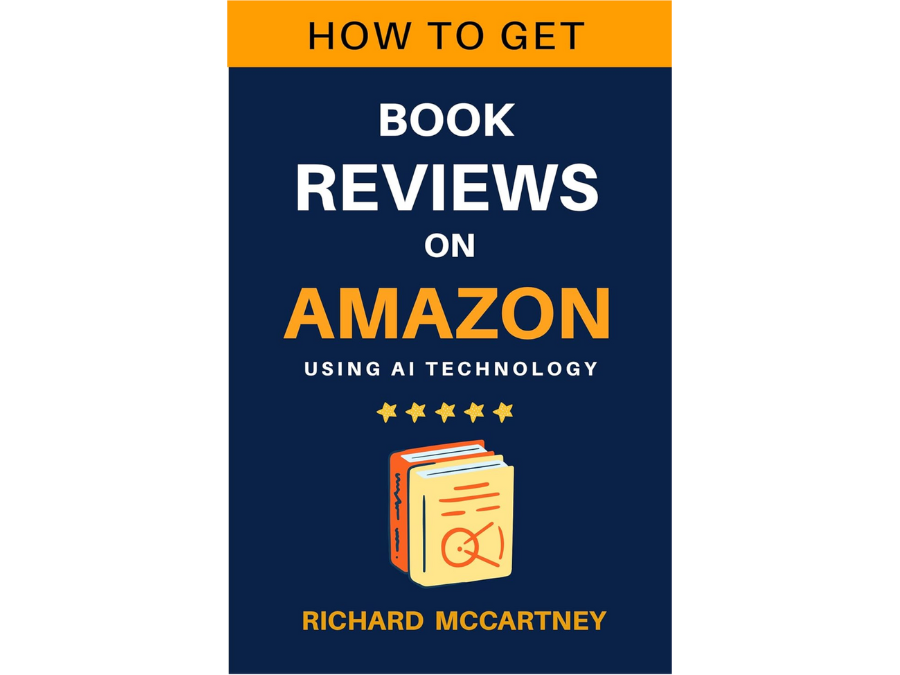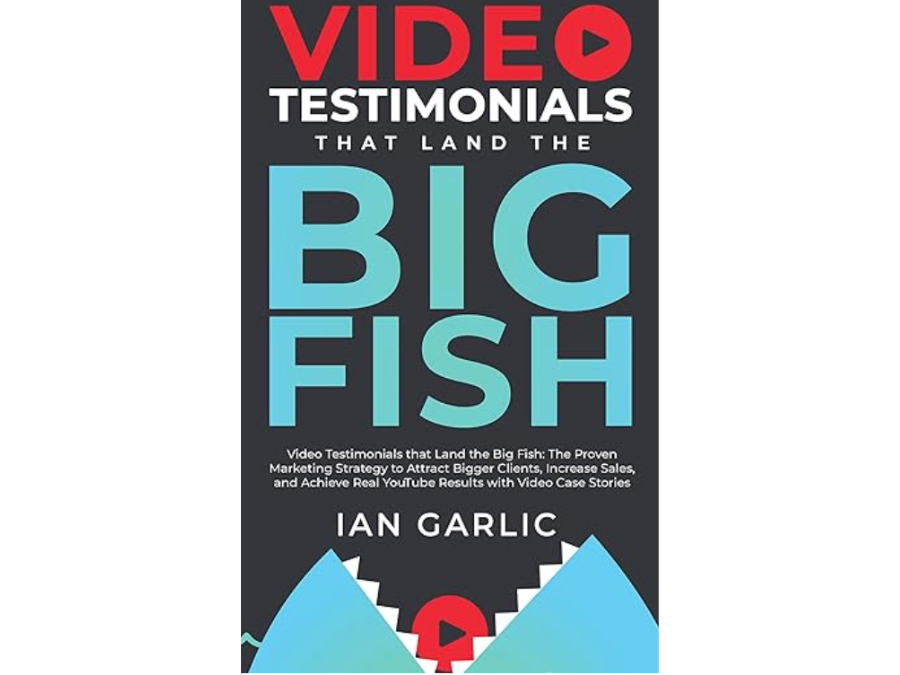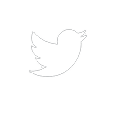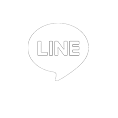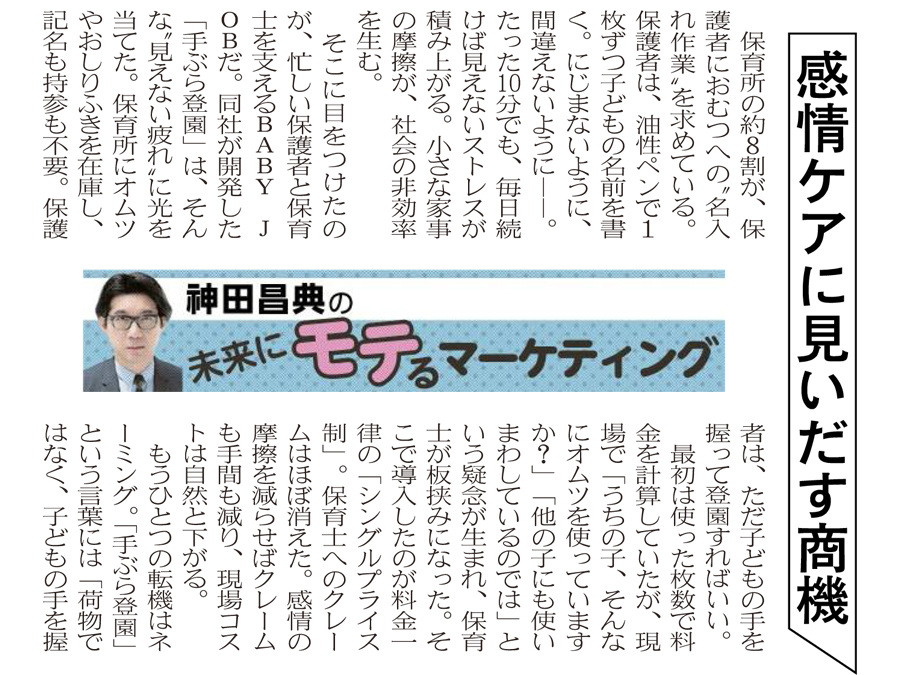
感情ケアに見いだす商機 ― 日経MJ連載「未来にモテるマーケティング」25/10/19号
2025/10/27
保育所の約8割が、保護者におむつへの〝名入れ作業〞を求めている。
保護者は、油性ペンで1枚ずつ子どもの名前を書く。にじまないように、間違えないように――。
たった10分でも、毎日続けば見えないストレスが積み上がる。
小さな家事の摩擦が、社会の非効率を生む。
そこに目をつけたのが、忙しい保護者と保育士を支えるBABY JOBだ。
同社が開発した「手ぶら登園」は、そんな〝見えない疲れ〞に光を当てた。
保育所にオムツやおしりふきを在庫し、記名も持参も不要。
保護者は、ただ子どもの手を握って登園すればいい。
最初は使った枚数で料金を計算していたが、
現場で「うちの子、そんなにオムツを使っていますか?」「他の子にも使いまわしているのでは」という疑念が生まれ、
保育士が板挟みになった。
そこで導入したのが料金一律の「シングルプライス制」。保育士へのクレームはほぼ消えた。
感情の摩擦を減らせばクレームも手間も減り、現場コストは自然と下がる。
もうひとつの転機はネーミング。
「手ぶら登園」という言葉には「荷物ではなく、子どもの手を握ってほしい」という願いが込められている。
単なるサービス名ではない。
〝理想の体験〞を先に言葉にした。その一言が共感の輪を広げた。
さらにBABY JOBは「解約を取りに行く」姿勢を貫いた。おむつ離れでおむつが不要になった家庭に、解約を促す。
普通なら損に見えるが、そこに誠実さが生まれ、保育士が胸を張って勧められるようになった。
今やBABY JOBが提供する「おむつサブスク」は、全国8400施設が利用。
2024年には東京プロマーケットに上場し、安定運営体制を整えた。
利用データは人工知能(AI)によって分析し、年齢や発達段階に応じた支援や商品開発への活用を検討している。
今後は、このデータを活用しながら、一人ひとりの発達や家庭環境に合わせた保育支援を目指す構想だ。
この仕組みの本質は、感情をデータとして捉えて仕組みの改善につなげる構造にある。
小さな不満を放置せず、サービスを磨き続ける。
その積み重ねが信頼を育て、やがて社会全体の効率を押し上げていく。
22年の経済協力開発機構(OECD)の報告書によると、
保育の質が高い国ほど出生率の回復と女性の就業率が両立する傾向がある。
「手ぶら登園」のような仕組みは、
保育者の負担軽減と就業支援を両立させる次世代型育児インフラとして注目を集めつつある。
台湾、フィリピンなどからも問い合わせが相次ぎ、日本の保育モデルが「育児インフラ」として評価され始めている。
少子化という課題が、皮肉にも日本を育児先進国へと押し上げつつある。
おもてなしの精神をAIによる感情データ活用と掛け合わせた社会モデル。
それは単に顧客を満足させる技術ではない。
人の心をすり減らさずに、日常を支える仕組みである。
おもてなしをAI時代に進化させた、感情ケアの仕組みづくり。
これはもしかすると、日本が世界に誇る次の競争力になるかもしれない。